私道の変更または廃止は建築基準法第45条にって制限されており、特定行政庁が禁止したり、制限することができます。
これは建築基準法上の接道義務違反を防ぐことが目的です。また、この規制は私的所有権と公共の福祉のバランスを図る制度ですから、私道所有者の権利が制限されてしまうのは仕方がない面もあります。
不動産購入時の重要事項説明書に「私道の変更または廃止の制限あり」と書かれている場合がありますが、一般的に心配する必要はありません。その点についても、記事後半で解説します。
- 「私道の変更または廃止の制限」の根拠となる建築基準法45条の趣旨
- 制限の対象となる位置指定道路や2項道路などの仕組み
- 不動産売買における重要事項説明のポイント
- 私道所有者の権利や義務とトラブル発生時の相談先
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。
私道の変更または廃止の制限とは公共の利益を守るルール

「私道の変更または廃止の制限」とは、たとえ個人の所有する私道であっても、その道が建築基準法上の道路として利用されている場合、所有者が一方的に変更したり廃止したりできないようにするルールです。
この制限は建築基準法第45条に定められており、不動産取引の際には物件の価値を左右する重要なポイントになります。
この制度は、個人の財産権よりも、その道路を利用する周辺住民の生活の安定や権利保護といった公共の利益を優先させる考え方に基づいています。
建築基準法第45条に基づく制度の概要
建築基準法第45条は、「私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が接道義務の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる」と定めています。
これは、私道の変更や廃止によって、その道路に面した建物が建て替えできなくなるなどの不利益を防ぐための規定です。
この法律により、対象となる私道の所有者は、自己の所有物であっても自由にその形状を変えたり、道をなくしたりすることができません。
具体的には、その私道を利用している土地や建物の権利者全員の同意がなければ、変更や廃止の手続きを進めることは極めて困難です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 根拠法規 | 建築基準法第45条 |
| 目的 | 私道に接する敷地の接道義務を維持し、建築行為の権利を保護 |
| 制限の内容 | 特定行政庁による私道の変更・廃止の禁止または制限 |
| 必要な手続き | 利害関係者全員の同意と特定行政庁の許可 |
この制度があるおかげで、私道に面した不動産の資産価値は法的に守られているのです。
なぜ個人の所有する私道が制限されるのか
所有権を持つ個人の私道が法律で制限される最大の理由は、その私道に接する他の土地の価値と権利を守るためです。
もし、所有者が自分の都合で自由に私道を封鎖したり、宅地に変更したりできると、大変な事態が起こります。
例えば、その私道しか公道への出入り口がない土地は、接道義務を果たせなくなります。
そうなると、その土地では建物の新築や建て替えができなくなり、資産価値は著しく下落します。
このような一方的な行為によって周辺住民が受ける不利益を防ぐことが、この制限の根本的な趣旨です。
個人の財産権は尊重されるべきですが、それが他者の権利を侵害し、公共の利益を損なう場合には、一定の制約を受けることになります。
接道義務との密接な関係
この制限を理解する上で欠かせないのが、「接道義務」です。
接道義務とは、建築基準法第43条で定められた、建物を建てるための基本的なルールで、「建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。
多くの宅地開発では、奥の土地がこの接道義務を満たすために、手前の土地所有者が敷地の一部を提供して私道(位置指定道路など)を造ります。
この私道が存在することで、初めて奥の土地に家を建てることが可能になります。
つまり、私道の変更・廃止の制限は、この接道義務を将来にわたって担保するために設けられた、いわば「車の両輪」のような関係にある制度なのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務の名称 | 接道義務 |
| 根拠法規 | 建築基準法第43条 |
| 道路の幅員 | 原則4m以上 |
| 接する長さ | 2m以上 |
この接道義務のルールがあるからこそ、私道を法的に保護する必要性が生まれます。
制限をかける特定行政庁の役割
私道の変更や廃止を実際に禁止・制限する権限を持つのが、「特定行政庁」です。
特定行政庁とは、建築主事を置く都道府県や市町村の長を指し、建築確認などの建築行政を担う機関です。
特定行政庁は、私道の変更や廃止の申請があった際に、それが建築基準法第45条に抵触しないかを審査します。
調査の結果、変更や廃止によって接道義務を満たさなくなる敷地が生じると判断した場合は、その行為を禁止または制限する命令を出せます。
また、道路の位置指定を行ったり、それらの道路情報を「指定道路図」として管理・公開したりするのも特定行政庁の重要な役割です。
彼らは単なる当事者間のトラブルを仲裁するのではなく、建築行政の専門家として、街全体の安全性や公共の利益を守るという公的な視点から判断を下します。
建築基準法第45条が定める私道制限の仕組み
私道に関する制限は、その道を利用する人々の建築する権利と財産価値を守るために存在します。
たとえ個人の土地であっても、建築基準法上の道路として指定されると、公共の役割を担うことになります。
そのため、所有者の一方的な都合で変更したり廃止したりすることはできません。
不動産取引で特に頻繁に登場する「位置指定道路」と「2項道路」は、どちらもこの制限の対象となる代表的な私道です。
| 道路の種類 | 作られた経緯 | 幅員 | 変更・廃止の原則 |
|---|---|---|---|
| 位置指定道路 | 宅地開発などで行政が位置を指定 | 原則4m以上 | 不可 |
| 2項道路 | 法施行前から存在し、道路とみなされた道 | 4m未満 | 不可 |
これらの仕組みを正しく理解することが、お客様へ適切な説明を行い、安心して取引を進めるための大前提となります。
制限の対象となる私道の種類
私道の変更・廃止の制限は、すべての私道に適用されるわけではありません。
対象となるのは、建築基準法上の道路として認められた特定の私道です。
具体的には、建築基準法第42条に定められた道路のうち、国や地方公共団体が所有する「公道」以外のものが該当します。
不動産売買の実務で遭遇する可能性が高いのは、特に位置指定道路(42条1項5号)と2項道路(みなし道路)の2種類です。
| 道路の種類(建築基準法) | 通称 | 概要 |
|---|---|---|
| 第42条1項5号道路 | 位置指定道路 | 宅地造成などに伴い、特定行政庁から位置の指定を受けた私道 |
| 第42条2項道路 | 2項道路(みなし道路) | 建築基準法施行時にすでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道 |
| 第42条1項3号道路 | 既存道路 | 建築基準法施行前から存在する幅員4m以上の私道 |
物件調査の際には、目の前の道がこれらのいずれかに該当するかどうかを役所の建築指導課などで必ず確認し、重要事項説明に反映させる必要があります。
位置指定道路(42条1項5号道路)の場合
位置指定道路とは、宅地を造成・分譲する際に、土地の所有者が特定行政庁(市役所など)に申請して「ここが道路です」と位置の指定を受けた私道のことです。
この道路は、複数の宅地が建築基準法の接道義務を満たすために計画的に造られるもので、原則として幅員が4m以上あることが指定の条件です。
一度指定を受けると、その道路に接する敷地は建築確認を受けることができます。
その代わり、道路としての公共性が確保されるため、所有者の都合だけで変更や廃止をすることは原則として認められません。
お客様に対しては、「この制限があるからこそ、将来にわたって道路がなくならず、建て替えの際も安心です」と、メリットとして説明することができます。
2項道路(みなし道路)とセットバック
2項道路とは、建築基準法が施行された昭和25年11月23日より前から建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が道路として指定したものを指します。
法律上、道路と「みなす」ことから「みなし道路」とも呼ばれます。
2項道路の最も重要な特徴がセットバック(後退)です。
将来的に4mの道幅を確保できるよう、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。
このセットバック部分は、たとえ登記上は自分の土地であっても、建築物を建てたり、門や塀を設けたりすることが法律で禁止されているのです。
セットバックが必要な物件は、登記簿上の面積よりも建築などに利用できる有効敷地面積が狭くなります。
この点は、不動産の価値に関わるため、お客様に正確に伝えることが不可欠です。
変更や廃止が認められる例外的な条件
原則として変更・廃止ができない私道ですが、公共の利益を損なわない特定の条件下であれば、例外的に認められるケースもあります。
その最も重要な条件は、その私道に接していたすべての敷地が、別の建築基準法上の道路に2m以上接道するなどして、接道義務を果たせる状態になることです。
例えば、大規模な区画整理によって私道の近くに新しい公道が整備され、私道を通らなくても各敷地が公道に出られるようになった場合などが考えられます。
ただし、この条件を満たした上で、さらにその私道に関係する土地・建物の所有者や借地権者といった利害関係者「全員」の同意を取り付け、特定行政庁の許可を得る必要があります。
変更・廃止に向けた手続きの流れ
私道の変更や廃止に向けた手続きは、利害関係者全員の合意形成から始まります。
これが全ての工程の中で最も難しく、重要なステップです。
全員の同意が得られた後に、初めて特定行政庁(市役所の建築指導課など)への申請が可能となります。
申請時には、利害関係者全員の同意書、測量図、変更後の計画図など、多くの専門的な書類を提出しなければなりません。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 事前相談 | 特定行政庁へ変更・廃止の実現可能性について相談 |
| 2. 利害関係者の特定 | 登記簿謄本や公図を取得し、土地・建物の所有者や借地権者などを調査 |
| 3. 全員の同意取得 | 全ての利害関係者から変更・廃止に関する同意書(実印と印鑑証明書)を取得 |
| 4. 申請書類の作成 | 申請書、理由書、位置図、測量図、同意書などを準備 |
| 5. 特定行政庁へ申請 | 準備した書類一式を提出 |
| 6. 審査・許可 | 行政による審査を経て、問題がなければ許可(または道路位置指定の取消し) |
この一連の手続きは、専門知識と多くの時間を要するため、実行する際には土地家屋調査士や弁護士などの専門家へ相談することが不可欠です。
不動産売買における重要事項説明のポイント
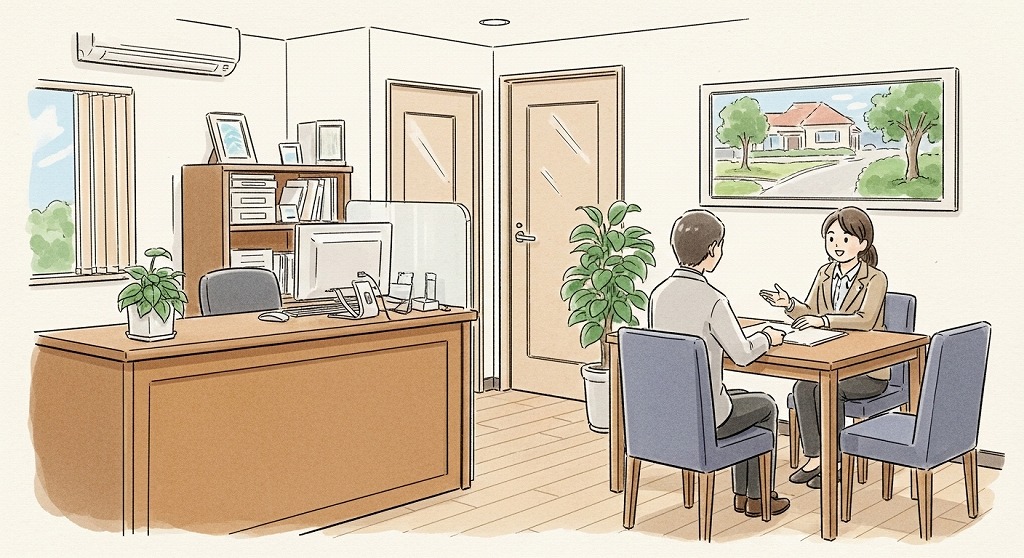
不動産売買、特に私道に接する物件を扱う際には、「私道の変更または廃止の制限」の有無を正確に調査し、買主様へ説明することが最も重要です。
この説明を怠ると、将来買主様が建物を建て替えられないなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、具体的な調査方法から重要事項説明書への記載例、そしてお客様の不安を和らげる説明のコツまで、宅地建物取引士として押さえるべきポイントを解説します。
取引前の事前調査の方法と指定道路図の確認
まず行うべきは、物件の前面道路が建築基準法上のどの道路に該当するのかを特定する調査です。
そのために不可欠なのが、特定行政庁(市役所や区役所の建築指導課など)で閲覧できる「指定道路図」になります。
これは、道路の種類や位置を地図上に示した公的な図面です。
国土交通省の指針によると、指定道路図は1/2,500以上の縮尺で作成され、道路の種類ごとに色分けされています。
この図面と「指定道路調書」を照合することで、前面道路が位置指定道路(42条1項5号道路)なのか、2項道路なのかといった正確な種別を確定できます。
| 調査ステップ | 確認事項 | 担当窓口(例) |
|---|---|---|
| 1. 事前準備 | 物件の地番を正確に把握 | 法務局(公図・登記事項証明書) |
| 2. 指定道路図の閲覧 | 道路の種類、位置、幅員 | 市区町村の建築指導課 |
| 3. 指定道路調書の確認 | 指定年月日、路線番号など詳細情報 | 市区町村の建築指導課 |
| 4. 現地調査 | 道路の現況幅員、境界標の有無 | — |
これらの調査を確実に行うことが、正確な重要事項説明の第一歩となります。
机上調査だけでなく、必ず現地で道路の状況を目で見て確認することも忘れないでください。
重要事項説明書への記載文例
調査で判明した事実は、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明書へ正確に記載する義務があります。
例えば、前面道路が位置指定道路であった場合、その事実は必ず記載します。たとえば、重要事項説明書には以下のように記載されるはずです。
【私道に関する負担等に関する事項】
本物件の前面道路(西側・幅員約4.0m)は、建築基準法第42条第1項第5号に定める道路(位置指定道路)であり、同法第45条の規定により、その変更または廃止が制限されます。このように、道路の種別と、変更・廃止が制限される根拠法条をセットで記載します。
購入時にそこまで不安にならなくてもいい理由
不動産を購入するときに「制限」といわれると、ネガティブに聞こえがちです。
しかし、一般論として私道部分は査定時に除外されているはずですし(つまりその分のお金はほとんど払っていないはずです)、こういった規定があるからこそ「今後も建て替えできる」と安心して住み続けることもできます。
私道にまつわる権利関係とトラブル対処
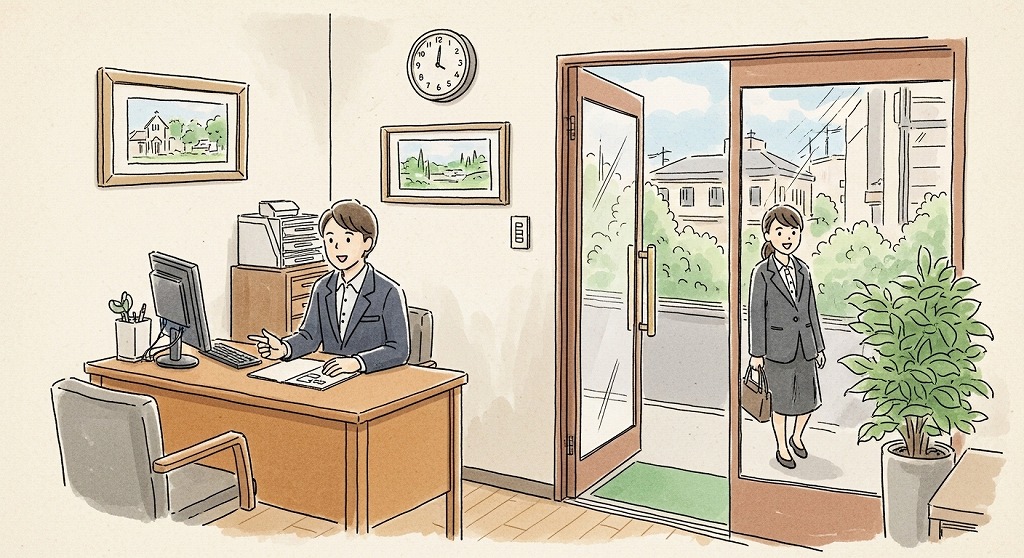
私道は個人の所有物でありながら、複数の人が利用することで複雑な権利関係が生じやすい場所です。
トラブルを未然に防ぎ、万が一発生した場合にも冷静に対処するためには、法律上の権利と義務を正しく理解しておくことが何よりも重要になります。
私道の権利関係を理解することは、安心して不動産取引を行うための第一歩です。
ここでは、通行権との違いや所有者が持つ権利と義務、そして具体的なトラブル事例と相談先について詳しく解説していきます。
通行権との違い
私道に関する権利を考えるとき、建築基準法上の道路としての利用と、民法上の「通行権」は分けて考える必要があります。
この2つは根拠となる法律と、権利が認められる目的が全く異なるのです。
建築基準法上の道路(位置指定道路など)は、その道路に接する敷地が「接道義務」を満たし、建物の建築を可能にすることを主な目的としています。
一方で、民法上の囲繞地(いにょうち)通行権などは、公道に出られない「袋地」の所有者が最低限の通行を確保するための権利です。
そのため、建築基準法上の道路であっても、隣人だからといって無条件に自動車での自由な通行までが当然に認められるわけではありません。
| 項目 | 建築基準法上の道路の利用 | 民法上の通行権(囲繞地通行権など) |
|---|---|---|
| 根拠法規 | 建築基準法 | 民法 |
| 主な目的 | 接道義務を満たし、建築を可能にすること | 袋地の所有者が公道へ出るための最低限の通行確保 |
| 権利の対象者 | 道路に接する敷地の所有者・利用者など | 袋地の所有者など、法律で定められた特定の者 |
| 通行の範囲 | 建築や日常生活に必要な範囲 | 公道へ出るための必要最小限の範囲 |
このように、どの法律に基づいた権利の話なのかを区別することが、問題を正しく理解する上で不可欠です。
私道所有者が持つ権利と維持管理の義務
私道の所有者は、その土地の所有者として権利を持つ一方で、安全な利用を維持するための義務も負います。
所有者の基本的な権利は、所有権に基づいてその私道を利用したり、処分したりする自由ですが、公共の利益のためにその権利は一定の制限を受けます。
所有者は、私道の通行方法についてルールを設けたり、上下水道管の埋設や掘削工事に対して承諾を与えたりする権利を持ちます。
その反面、私道の舗装が傷んだ場合の補修や、側溝の清掃といった維持管理を行う義務を負います。
固定資産税の支払いも義務の一つです。
万が一、道路の陥没などで通行人が怪我をした場合は、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。
| 区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権に基づく利用・収益・処分 |
| 通行方法のルール設定(著しい制限は不可) | |
| 上下水道管などの埋設に対する承諾(承諾料請求) | |
| 掘削工事などの承諾 | |
| 義務 | 舗装の補修や清掃などの維持管理 |
| 固定資産税・都市計画税の納税 | |
| 第三者への損害賠償責任(工作物責任) |
所有者としての権利を主張するだけでなく、こうした義務もしっかりと果たしていくことが、利用者との良好な関係を築く上で大切になります。
私道をめぐるよくあるトラブル事例
私道をめぐるトラブルの多くは、当事者間のコミュニケーション不足や権利関係に関する認識のズレから発生します。
感情的な対立に発展しやすく、一度こじれると解決が難しくなるケースも少なくありません。
例えば、土地の相続によって所有者が変わった際に、新しい所有者がこれまで無料で通行していた近隣住民に対して突然通行料を請求するケースがあります。
他にも、私道上に物を置いて通行を妨害したり、特定の人の車両通行を禁止したりといった問題も起こりがちです。
特に費用の負担についてはトラブルになりやすく、アスファルトの補修費用を誰がどれだけ負担するのかで揉めることは珍しくありません。
- 通行料の請求: 新しい所有者が突然、高額な通行料を請求してくる
- 通行の妨害: 特定の車両の通行を禁止されたり、物を置かれたりする
- 駐車トラブル: 私道内に無断駐車され、通行の妨げになる
- 維持管理費の負担: 舗装の補修費用を誰がどれだけ負担するかで揉める
- 掘削承諾の拒否: 上下水道管の工事に必要な掘削の承諾が得られない
- 相続による所有者変更: 相続人が私道の存在を知らず、利用を制限しようとする
ういったトラブルは、当事者だけで解決しようとすると感情論になりがちです。問題が大きくなる前に、専門家へ相談するほうが確実でしょう。
問題発生時の相談先とその選び方
私道トラブルが発生し、当事者間での話し合いによる解決が難しいと感じた場合は、一人で抱え込まずに、第三者の専門家へ相談することが解決への近道です。
例えば、隣地との境界が不明確になっている場合は土地家屋調査士、権利関係の交渉や法的な解決(調停・訴訟)を望むのであれば弁護士が適任です。
また、通行地役権などの登記手続きが必要であれば司法書士に相談します。
そもそも前面道路が建築基準法上のどの道路にあたるのかといった行政上の確認は、市役所の建築指導課などが窓口です。
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 権利関係の交渉、調停、訴訟 | 弁護士 |
| 境界の確定、測量 | 土地家屋調査士 |
| 登記(通行地役権設定など) | 司法書士 |
| 道路の種別や建築に関する行政手続き | 特定行政庁(市役所の建築指導課など) |
| 不動産の価値、売買に関する相談 | 宅地建物取引士(不動産会社) |
専門家を選ぶ際には、料金だけでなく、不動産問題、特に私道に関するトラブルの解決実績が豊富かどうかを確認することが大切です。
多くの事務所では初回相談を設けているため、まずは話を聞いてもらい、信頼できる専門家かどうかを見極めましょう。
よくある質問(FAQ)
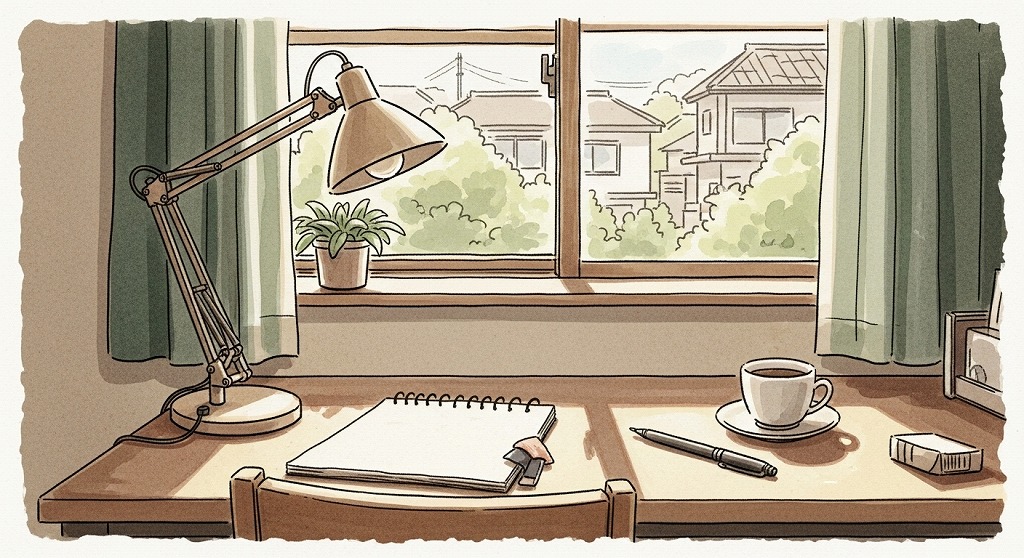
- Q「私道の変更または廃止の制限」とは、簡単に言うと何ですか?
- A
個人の所有物である私道でも、その道が建築基準法上の道路として認められている場合、所有者の一存で自由に変更したり無くしたりできない、という決まりのことです。
これは、その道路を利用している他の土地所有者が、家の建て替えができなくなるなどの不利益を受けないようにするための、公共の利益を守る大切なルールになります。
- Q自分の土地なのに、なぜ私道を自由に変更・廃止できないのですか?
- A
建物を建てる際には、その敷地が建築基準法で定められた道路に2m以上接している必要があります。
これを「接道義務」と呼びます。
もし私道の所有者が自由に道を廃止できてしまうと、その私道を利用していた他の土地がこの接道義務を果たせなくなり、資産価値が大きく下がるなどの問題が生じます。
個人の私道所有者の権利よりも、周辺住民が建物を建てられる権利を守ることが優先されるため、法律による制限が設けられています。
- Q2項道路の「セットバック」した部分は、どうなるのでしょうか?
- A
セットバックした部分は、登記上はご自身の土地であっても、法律上は「道路」とみなされます。
そのため、建築物を建てたり、門や塀を設置したりすることはできません。
これは、将来的に道幅を4m確保し、緊急車両の通行などをスムーズにする公共の目的があるからです。
この建築制限は不動産の価値に直接影響するため、不動産売買の際は特に重要な注意点となります。
- Q私道として使っている土地にも、固定資産税はかかりますか?
- A
はい、原則として私道も個人の資産ですので、所有者には固定資産税や都市計画税が課税されます。
ただし、自治体によっては、不特定多数の人が自由に通行できる「公衆用道路」として利用されているなどの一定の条件を満たす場合に、申請によって固定資産税が減免または非課税になる制度があります。
詳しい条件は、その土地がある市町村の資産税課にご確認ください。
- Qもし私道の所有者が道を封鎖したら、どうすれば良いですか?
- A
建築基準法上の道路として認められている私道を正当な理由なく封鎖する行為は、法律に違反する可能性が高いです。
まずは特定行政庁(市役所の建築指導課など)に状況を相談してください。
行政から所有者へ指導が入ることがあります。
それでも私道トラブルが解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談し、通行を妨害しないよう求める法的な手続きを検討することになります。
- Qどうしても私道を廃止したい場合、どんな手続きが必要ですか?
- A
私道の廃止は原則として認められませんが、例外的なケースでは可能です。
最も重要な条件は、その私道に接している全ての土地が、別の道路に接続するなどして、接道義務を果たせる状態になることです。
この条件を満たした上で、土地や建物の所有者、借地権者といった利害関係者「全員」から実印と印鑑証明書付きの同意書を取り付け、特定行政庁へ申請し許可を得る必要があります。
この私道 廃止 手続きは非常に難易度が高いです。
まとめ

この記事では、個人の所有物である私道が、建築基準法第45条によってなぜ変更・廃止を制限されるのか、その仕組みと不動産取引における重要事項説明のポイントを解説しました。
この制度は、その私道に接するすべての土地が将来にわたって建物の建築や建て替えができる状態(接道義務)を法的に守るための、非常に重要なルールです。
- 私道の変更や廃止は周辺敷地の「接道義務」を守るために制限
- 位置指定道路や2項道路などが主な対象
- 不動産取引では正確な調査と重要事項説明が不可欠
- 買主には「制限」ではなく「将来の安心材料」というメリットとして説明可能
私道に関する制限は、お客様の大切な資産を守るための仕組みです。
この記事で得た知識を基に、まずはご担当の物件の前面道路がどの種類の道路にあたるのか、役所の「指定道路図」で改めて確認することから始めてみましょう。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

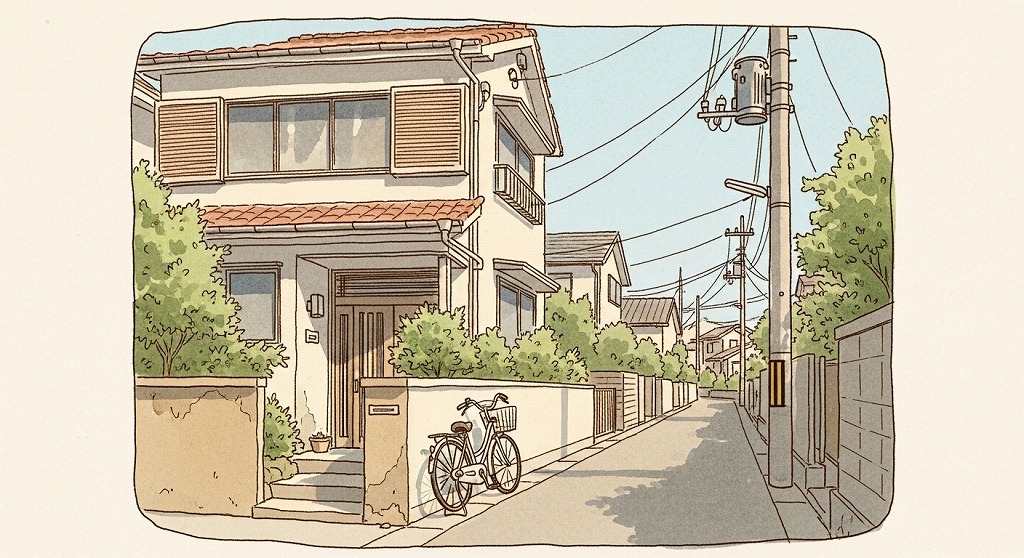


コメント