幅員1.8m未満の道路に接する土地は、建築基準法第42条第2項が定める二項道路の要件を満たさず、法律上「道路」ではなく「通路」として扱われるため、原則として再建築が認められません。
建築基準法第42条第2項の二項道路として指定を受けるには、現況幅員が1.8m以上であることが必須要件とされており(同法第42条第6項)、これを下回る場合、建築基準法第43条が定める接道義務を満たさないため、建築確認が下りないからです。
ただし、解決策がないわけではありません。建築基準法第43条第2項第2号に基づく「特例許可」を特定行政庁から取得できれば、建築審査会の同意のもと、例外的に建築が認められる可能性があります。
本記事では、幅1.8m未満の通路に接する土地が直面する法的制約と資産価値への影響を、建築基準法の条文に基づき正確に解説します。さらに、特例許可の具体的な取得プロセス、自治体別の許可基準の比較(大阪府・吹田市・横浜市・京都市)、そして狭あい道路拡幅整備事業との戦略的連携など、実務的な解決策を詳述します。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。
そもそも「二項道路」とは?基本をやさしく解説

幅員1.8m以下の二項道路に原則として建築が認められない理由を考えるには、まず「そもそも二項道路とは何か」を再確認する必要があります。具体的に見ていきましょう。
二項道路の定義
二項道路(にこうどうろ)は、正式には「建築基準法第42条第2項に定める道路」のことです。別名「みなし道路」とも呼ばれます。
建築基準法では、原則として「幅4m以上の道路に2m以上接していないと、建物を建ててはいけない」というルールがあります。このルールの背景には、災害時の消防車や救急車の進入路を確保する、住民の避難経路を守る、そして良好な住環境を維持するという明確な目的があります。
しかし、建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日より前から、すでに建物が立ち並んでいた狭い道については、幅が4m未満でも「道路」として認めましょうという救済措置が設けられました。これが二項道路です。既存の市街地の実態に法を適合させ、住民の生活基盤を保護する目的で設けられた制度といえます。
二項道路として認められる3つの条件
二項道路として指定されるために、法令で定められた要件があります。まず、現況の幅が1.8m以上であり、かつ4m未満であること。この「1.8m以上」という下限値が、今回の記事で最も重要なポイントです。
次に、1950年11月23日という基準時において、現に建築物が立ち並んでいた道であることが必要です。単に古くからある狭い道というだけでは不十分で、基準時に実際に建物があったという歴史的な事実が求められます。
そして最後に、特定行政庁(都道府県知事または市町村長)が、これらの要件を確認した上で、公式に「二項道路」として指定することが不可欠です。行政の指定行為がなければ、どんなに古い道でも二項道路にはなりません。
二項道路に指定された場合、その中心線から水平距離で2mの線が道路の境界線とみなされ、将来的に4mの幅員を確保することが前提とされます。これを「セットバック」といいます。
なぜ1.8m未満だと問題なのか?法的な構成を理解する
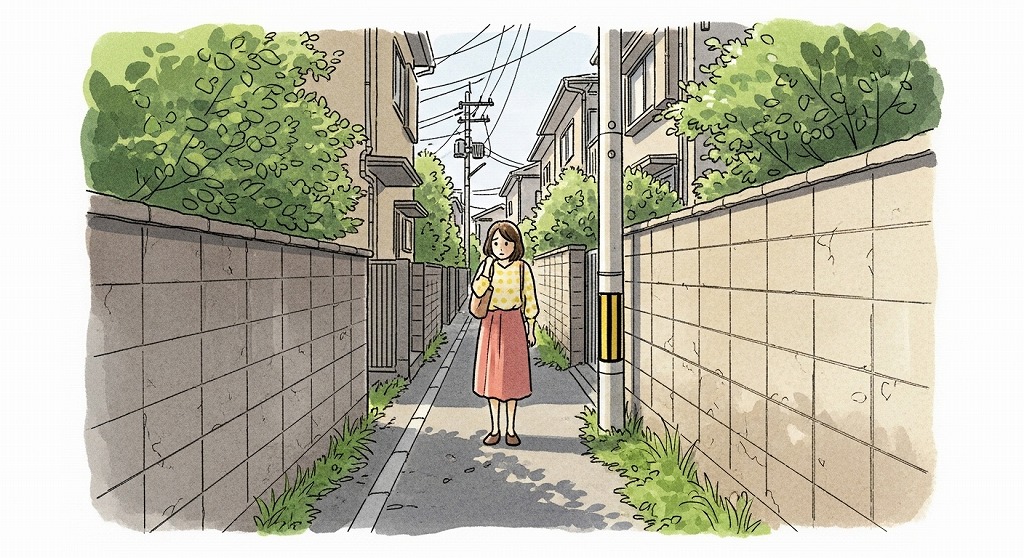
道幅が1.8m未満の場合、次のような法的構成となります。まず、幅1.8m以上という最低条件を満たしていないため、建築基準法第42条第2項に定められる二項道路の要件から外れてしまいます。
その結果、この通路は法的に「道路」として認められず、単なる「通路」または「空地」として扱われることになります。
そして、敷地が法的な「道路」に接していないため、建築基準法第43条が定める「接道義務」に違反する状態となり、最終的に建物の新築や増改築が原則として不可能、すなわち「再建築不可」物件と判断されるのです。
「道路」と「通路」の違いが生む大きな差
この「道路」と「通路」の違いは、単なる言葉の問題ではありません。それは、適用される法体系そのものを根本的に変える重要な区別です。
敷地が法的な「道路」に接している場合、たとえ狭い二項道路であっても、所有者にはセットバックなどの明確な義務と、それに伴う建築の権利が与えられます。つまり、敷地を後退させれば建築できるという道筋が明確に示されているのです。
一方で、敷地が法的な「通路」にしか接していない場合、所有者には建築に関する固有の権利は存在しません。建築を可能にするためには、行政の裁量による特例的な「許可」を別途求めなければならないのです。この法的地位の根本的な違いを認識することが、問題解決に向けた第一歩となります。
再建築不可になると何が困るのか?5つの深刻なデメリット
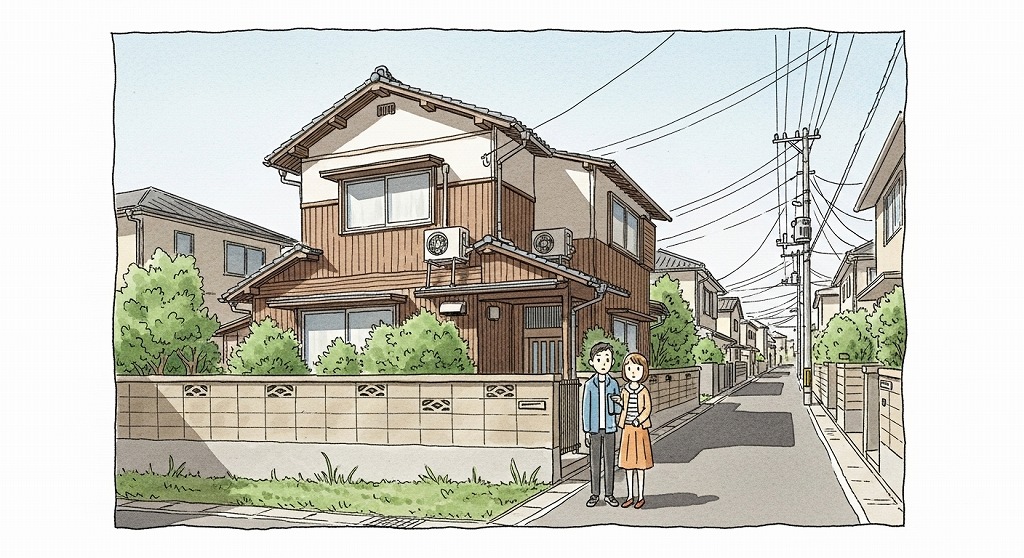
再建築不可になると、活用や売却がしづらくなることで資産価値が下がってしまいます。ここでは、再建築不可物件の具体的なデメリットを見ていきましょう。
建て替えができない深刻さ
接道義務を満たさない敷地は、法的に「再建築不可」となります。これでは、既存の建物を解体して新しい建物を建てることができません。さらに、その影響は新築だけに留まりません。建築確認申請を必要とする大規模なリフォームや増築も不可能です。
建築確認が不要な範囲の小規模な内装リフォームなどは可能ですが、建物の構造や規模に関わる変更は一切できなくなり、不動産としての利用可能性は著しく制限されます。老朽化が進んでも根本的な対策が取れないという状況に陥るのです。
資産価値への甚大な影響
「再建築不可」という法的制約は、不動産の資産価値に直接的かつ甚大な影響を及ぼします。市場における評価額は、近隣の建築可能な土地と比較して大幅に低くなるのが一般的であり、その価格は通常の5割から7割程度、あるいはそれ以下になることも珍しくありません。
売却の際には、購入希望者の層が極めて限定されます。金融機関は、再建築ができない不動産を担保として評価しないため、住宅ローンの融資がほぼ不可能となります。これにより、購入者は自己資金で一括購入できる者に限られ、市場性は著しく低下します。不動産取引においては、この「再建築不可」という事実は、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明書」において買主へ明確に告知する義務がある最重要項目の一つであり、これを怠った場合は深刻な法的責任を問われることになります。
税制上の二律背反
資産価値の低下は、税金の評価額にも反映されます。固定資産税や都市計画税、そして相続税の算定基準となる固定資産税評価額は、再建築不可の不動産については低く評価される傾向にあります。特に相続税評価においては、「無道路地」として扱われ、通常の土地評価額から大幅な減価補正が適用されることがあります。
これは税負担の軽減という側面を持つ一方で、資産価値そのものが低いことの裏返しでもあります。節税にはなるものの、本来の資産価値が失われているという現実からは目を背けることができません。
相続と親族間紛争のリスク
「再建築不可」物件の相続は、単なる資産の承継ではなく、問題の承継となり得ます。相続人は、建物の老朽化が進んでも建て替えができず、売却しようにも買い手が見つからず、担保としての活用もできないという八方塞がりの状況に直面する可能性があります。
このような不動産は、物理的な資産から、むしろ管理コストや親族間の対立を生む「負の資産」へと変貌するリスクをはらんでいます。相続人が複数いる場合、一人は現状維持での居住を望み、別の一人はたとえ安価でも売却して現金化したいと考え、また別の一人は費用と時間をかけて法的な解決を目指したいと考えるかもしれません。このように、法的制約に起因する利用や処分の困難さが、相続人間の利害対立を先鋭化させ、解決困難な家族問題へと発展するケースは少なくないのです。
【解決策】建築基準法第43条第2項の特例許可とは
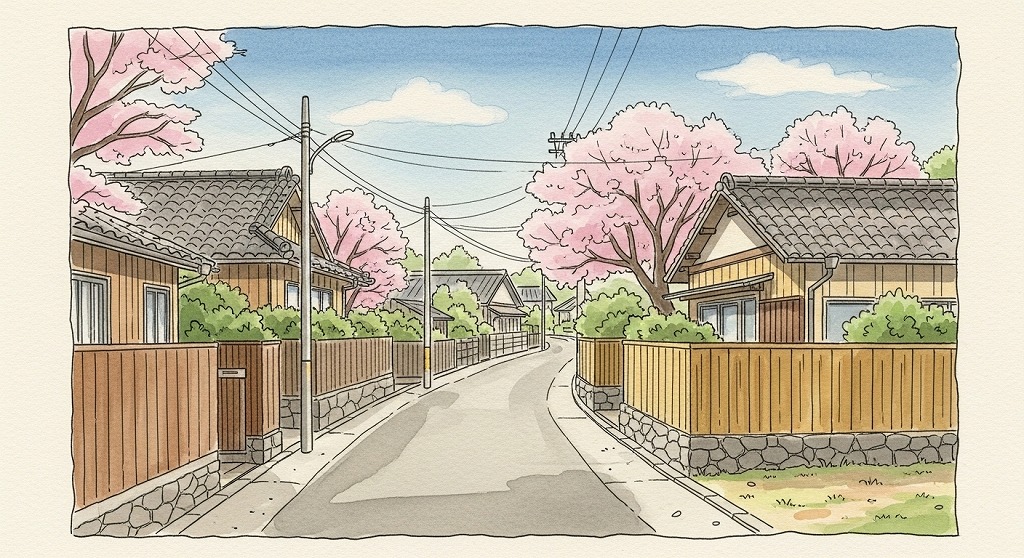
接道義務を満たさない敷地に対する救済措置として、建築基準法第43条第2項が定められています。この条項は、特定行政庁が「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認める場合に限り、例外的に建築を許可または認定することを可能にするものです。
この制度の存在により、幅1.8m未満の通路にしか接していない敷地であっても、適切な手続きを経れば建築できる道が残されています。ただし、決して簡単な道のりではありません。
「認定」と「許可」の2つの手続き
第43条第2項には、二つの異なる手続きが存在します。第1号は「認定制度」と呼ばれ、農道など特定の要件を満たす道に接する場合など、あらかじめ法令で定められた基準に適合するケースについて、特定行政庁が認定を行う比較的簡素な手続きです。この手続きは建築審査会の同意を必要としません。しかし、幅員1.8m未満の通路に接するケースは、通常この認定制度の対象とはなりません。
一方、第2号は「許可制度」と呼ばれ、本稿の主題である幅1.8m未満の通路に接する敷地が目指すべき手続きです。これは、個別の敷地状況や建築計画を審査し、特定行政庁が裁量によって建築を許可するものであり、その判断には建築審査会の同意が不可欠とされています。建築審査会は、建築行政における専門的かつ中立的な第三者機関であり、複雑な案件や例外的な許可について、その妥当性を審査する重要な役割を担っています。
許可取得までの具体的なプロセス

許可取得までの道のりは、一般的にいくつかの段階を経て進められます。まず最も重要なのが事前協議です。正式な申請に先立ち、管轄の市区町村の建築指導課などと事前協議を行うことが極めて重要です。これは、計画の実現可能性や、申請にあたっての論点、必要書類などを確認するための不可欠なステップです。
事前協議を怠っていきなり正式申請をしても、基本的な要件を満たしていなかったり、必要な書類が不足していたりして、時間とお金の無駄になる可能性が高くなります。行政の担当者と顔を合わせ、率直に相談することで、成功への道筋が見えてくることも多いのです。
書類準備と最大の難関
事前協議で方向性が見えたら、次は必要書類の準備です。申請には膨大な書類の提出が求められます。一般的なものとして、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、公図の写し、敷地および通路の現況写真、登記事項証明書などが挙げられます。
しかし、手続きにおける最大の難関は、書類の作成ではありません。通路として利用している土地の所有者全員からの同意書の取得が、最も困難かつ重要なポイントとなります。この通路が複数の所有者による共有名義である場合、一人でも同意を拒否すれば、その時点で申請は事実上不可能となります。
これは、法が通路の共同利用者に事実上の拒否権を与えていることを意味します。申請の成否が、建築計画の技術的な妥当性だけでなく、近隣住民との交渉能力や人間関係に大きく左右されることを示しているのです。所有者の中に連絡が取れない人がいる場合や、過去にトラブルがあった場合などは、さらに困難が増します。
審査から許可まで
全ての書類を整え、申請手数料を納付して正式に申請を行います。行政庁による書類審査の後、案件は建築審査会に付議され、同意の可否が審議されます。建築審査会の同意が得られ、行政庁が最終的に許可を決定すると、許可書が交付されます。この許可書を取得して初めて、通常の建築確認申請手続きに進むことができます。
このプロセス全体は、時間と費用、そして多大な労力を要するものです。通常、数か月から1年以上かかることもあり、専門家である建築士や弁護士の支援が不可欠となる場合が多いのが現実です。
自治体によって基準が大きく異なる!具体例で比較

建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可の具体的な基準は、国が一律に定めているわけではなく、各特定行政庁(都道府県や市)が、それぞれの地域の実情に応じて「許可取扱基準」や「要領」といった形で独自に定めています。
したがって、建築の可否を判断するためには、必ず当該敷地が所在する自治体の担当窓口で、適用される基準を直接確認することが絶対条件となります。隣の市では許可されるケースでも、自分の市では認められないということが普通にあり得るのです。
自治体別許可基準の比較
公開されている情報に基づき、いくつかの自治体の許可基準を比較すると、基準の多様性と地域の実情に応じた工夫が見えてきます。
大阪府では、階層的な基準を設けており、1.5m以上1.8m未満などの幅員に応じて個別案件ごとに判断しています。建物の用途は専用住宅、二世帯住宅、小規模な兼用住宅に限定し、高さ10m以下、3階以下などの規模制限があります。通路が通り抜け可能か行き止まりかを区別し、行き止まりの場合は延長距離の制限も設けています。
吹田市の基準は特に詳細で、0.9mという非常に狭い幅員まで具体的な基準を設けています。建物は戸建住宅に限定され、通路の形態によって規模が異なります。通り抜け通路の場合は3階以下、行き止まり通路の場合は2階以下としています。また、耐火または準耐火構造への強化を求め、行き止まりの場合は一方後退が必要とされるなど、詳細な規定があります。1970年時点で建ち並びがなければ合意が必要など、歴史的な要件も加わります。
横浜市でも同様に階層的な基準があり、「個別同意基準」として0.9m以上1.8m未満の通路に対応しています。基準により高さや階数の制限があり、「路線型」と「専用型」の通路を区別しています。通路中心線からの後退距離として2mまたは1.35mなどが求められます。
戦略的示唆
この比較から、いくつかの重要な戦略的示唆が読み取れます。吹田市の基準が極めて詳細であることは、同市がこうした案件に数多く対応してきた歴史を持ち、困難ではあるが確立された手続きが存在することを示唆しています。
また、狭隘な通路に面する場合に耐火性能の強化を求める規定は、「建築は許可するが、その代償として通常以上の防災性能を求める」という行政と申請者間のトレードオフの関係を明確に示しています。このように、各自治体の基準を詳細に分析することで、申請を通すための戦略を立てることが可能となるのです。
京都市の先進的な取り組み
京都市では、歴史的な路地を守りながら防災性を高めるため、独自の道路指定制度を設けています。幅1.8m未満の道でも、一定条件下で2項道路に指定できる仕組みがあります。基準時の道幅が1.5m以上(両端が既存の2項道路に接続しているなど道路の連続性を確保する必要がある場合は0.6m以上)であることが求められます。
袋路(行き止まり道路)の場合は、延長距離70m以内であること、または他の道路や公園などに通り抜ける避難経路を有することが条件となります。また、後退距離の緩和(3項道路指定)により、敷地後退を道路の中心線から1.35m以上2m未満に緩和できる制度もあります。
京都市のように、歴史的な町並みを守りながら防災性を高めるという、地域の実情に合わせた柔軟な基準を設けている自治体もあるのです。こうした制度を知ることで、「絶対に無理」と思っていた状況にも、解決の糸口が見えてくることがあります。
他の解決策も検討しよう
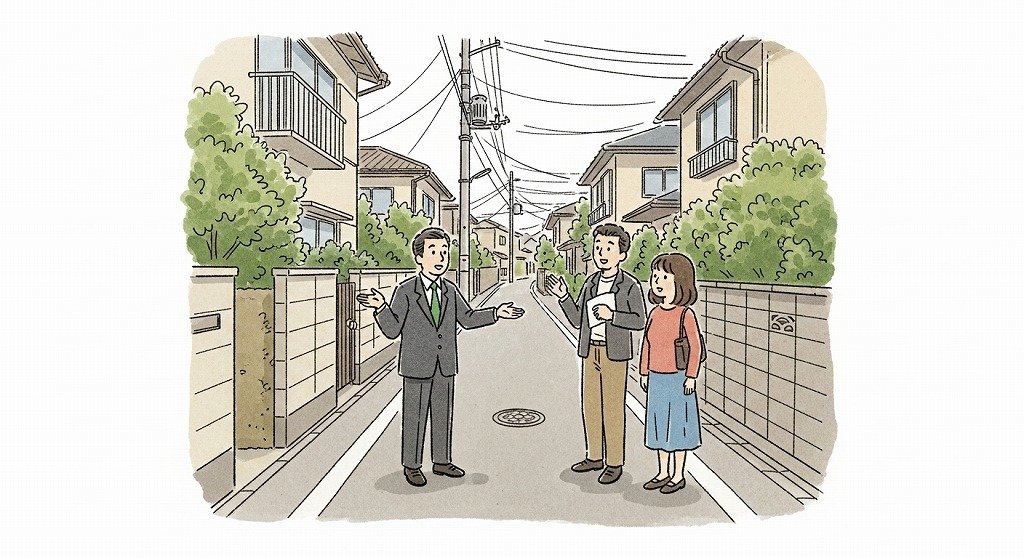
最も根本的な解決策は隣地の取得
最も根本的かつ効果的な解決策は、隣接する土地の一部を購入または賃借し、自身の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接するようにすることです。これにより、「再建築不可」という法的制約そのものが解消され、不動産の資産価値は劇的に向上します。
この方法の最大のメリットは、特例許可の複雑な手続きや、通路所有者全員からの同意取得といった困難なプロセスを回避できることです。一度道路に接道すれば、その後は通常の建築確認申請だけで建築が可能になります。
ただし、この方法には高いハードルがあります。隣地所有者の協力が前提であり、多額の費用を要するため、実現のハードルは非常に高いのが現実です。隣地所有者が売却や貸与を拒否すれば、それ以上進めることはできません。また、土地の価格交渉、測量、分筆登記など、様々な手続きとコストがかかります。
狭あい道路拡幅整備事業の戦略的活用
多くの地方自治体では、防災性の向上と住環境の改善を目的として、「狭あい道路拡幅整備事業」を推進しています。この事業は、二項道路などの幅員4m未満の道に接する敷地で建築行為が行われる際に、所有者が自主的に敷地を後退(セットバック)し、道路を拡幅することに対して支援を行うものです。
自治体が提供する支援内容は多岐にわたります。一般的には、セットバック部分にある門や塀などの撤去費用、測量や分筆登記費用、拡幅部分の舗装費用などに対する助成金の交付があります。また、所有者がセットバックした土地を自治体に寄付する制度や、自治体が買い取る制度もあります。さらに、寄付または無償使用を承諾したセットバック部分の土地について、固定資産税や都市計画税を非課税または減免する措置が取られることもあります。
ここで重要なのは、第43条第2項の許可申請と、この狭あい道路整備事業を戦略的に結びつけることです。自治体の公共政策上の目標は、安全なまちづくりのために狭い道を拡幅することにあります。一方で、土地所有者の目標は、建築許可を得ることです。
したがって、第43条第2項の許可を申請する際に、単に「建築させてほしい」と要求するのではなく、「自治体の狭あい道路整備事業に協力し、自主的に敷地を後退させて通路の拡幅に貢献するので、特例として建築を許可してほしい」という形で提案を行うことが考えられます。このように、所有者の私的な利益と、行政の公益的な目標を一致させるアプローチを取ることで、行政や建築審査会に対して、より協力的で前向きな印象を与えることができます。これは、裁量的な許可を得る上で、心理的にも有利に働く可能性があるのです。
購入を検討している場合、絶対に確認すべきこと

再建築不可の可能性がある物件を購入する場合、徹底した事前調査(デューデリジェンス)が不可欠です。購入してから「建て替えができない」と気づいても、取り返しがつきません。
まず、市区町村の建築指導課に赴き、前面通路の正確な幅員と法的地位(道路か否か)を公式に確認しましょう。不動産業者の説明だけでなく、必ず自分で行政に確認することが重要です。行政の担当者に、現地の状況を説明し、建築基準法上どのような扱いになるのかを明確に聞いておきましょう。
次に、購入契約を締結する前に、具体的な建築計画の概要を携えて行政と事前協議を行い、第43条第2項許可の見込みについて感触を得ることが重要です。「許可が下りる可能性はありますか」という抽象的な質問ではなく、具体的な建築プランを示して相談することで、より正確な判断材料が得られます。
通路の所有者を登記簿で全て確認し、全員から同意を得られる現実的な可能性があるかを見極めることも必要です。所有者が遠方に住んでいたり、連絡先が不明だったり、過去にトラブルがあったりする場合は、同意取得が極めて困難になります。
そして、許可申請にかかる専門家報酬、測量費、そして許可取得の不確実性といったリスクを、物件価格と合わせて総合的に評価しましょう。いくら物件価格が安くても、許可取得に数百万円かかったり、最終的に許可が下りなかったりするリスクを考慮する必要があります。
売主の完全な情報開示義務
当該物件を売却する場合、完全な情報開示が法的に求められます。「再建築不可」であること、その法的根拠、そして第43条第2項許可の可能性がある場合はその手続きの困難さも含め、全ての情報を買主に正確に開示する義務があります。
透明性の確保が、後の紛争を避けるための最善策です。購入者層は、隣地を取得して接道義務を解消しようとするデベロッパーや、再建築を前提としない利用(倉庫、資材置き場、駐車場など)を考える現金購入者などに限定されることを理解しておく必要があります。
また、売却前に建物を解体するか否かは慎重な判断を要します。更地にすることで土地の形状は分かりやすくなりますが、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり税額が上昇するリスクがあります。また、既存不適格建築物としての地位を失うことにもなります。
まとめ:冷静な判断と専門家の活用が鍵

幅員1.8m未満の通路に接する不動産は、建築基準法上の「二項道路」には該当せず、原則として「再建築不可」という厳しい法的制約下に置かれます。この状況を打開するための主な道は、建築基準法第43条第2項第2号に基づく特定行政庁の特例的な「許可」を取得することです。
しかし、その許可基準は各自治体の裁量に委ねられており、申請プロセスは通路所有者全員の同意を必要とするなど、極めて困難かつ不確実性が高いものです。決して簡単な道のりではありませんが、絶望的な状況とは限りません。
当該不動産の所有者、または購入を検討する者が取るべき行動として、まず最優先すべきは行政への相談です。何よりもまず、敷地の所在地を管轄する市区町村の建築指導課に連絡を取り、公式な見解と適用される「許可取扱基準」を確認することが全ての出発点となります。
次に、自治体の許可基準を詳細に分析し、自身の計画がその要件を満たす可能性があるかを検討しましょう。通路の権利関係を登記簿で完全に把握し、全ての権利者から同意を得られる現実的な見込みがあるかを冷静に評価することも重要です。
そして、この種の案件に精通した一級建築士や弁護士に相談し、専門的な知見に基づく戦略を立てることをお勧めします。特に、当該自治体での申請経験が豊富な専門家を見つけることが望ましいでしょう。短期的な目標である建築許可の取得と、長期的な視点である自治体の道路拡幅事業への参加を組み合わせ、行政との協調的な関係を築くアプローチを検討することも有効です。
この問題は、法的にも実務的にも極めて複雑です。しかし、地方分権化された許可基準の中に、地域の実情に合わせた解決の道が示されている場合もあります。正確な法的知識に基づき、専門家と連携し、行政や近隣住民と粘り強く交渉する戦略的なアプローチこそが、この困難な状況を乗り越え、不動産の価値を再生させるための最も確実な道筋なのです。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

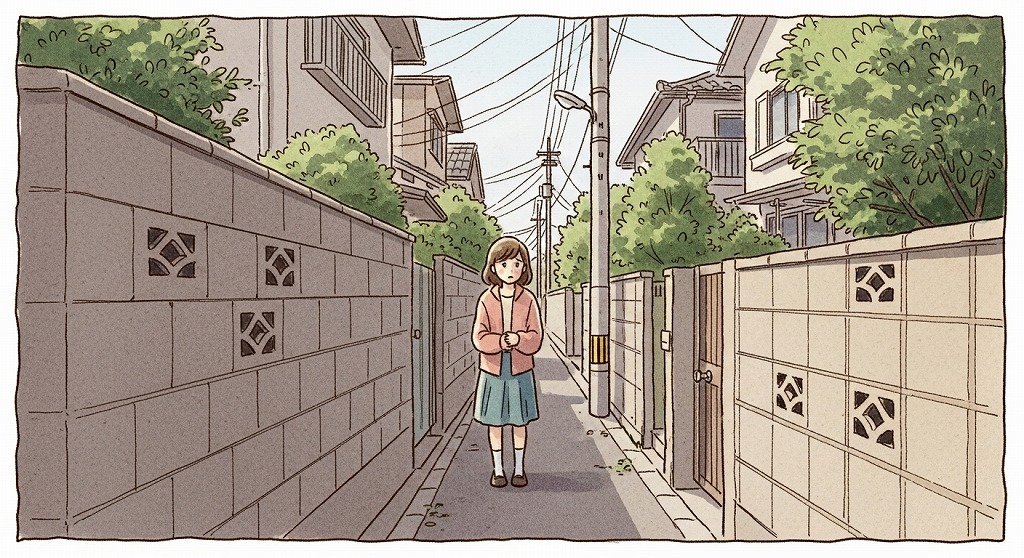


コメント