敷地の一部が「私道」として利用されている、というのは何かとめんどうなものです。
アスファルトのひび割れ補修や側溝の清掃、将来の上下水道管の交換費用などの管理負担は年々のしかかってきます。
そんな悩みを根本的に解決できる方法が「私道の市道認定」です。これは、私道を市に無償で寄付し、公道として認定してもらう手続きのことで、認定後は道路の維持管理や補修費用の負担が市町村に移ります。
さらに、将来の不動産売買や相続時に起こりがちな「売却漏れ」といったトラブルも未然に防げるため、長期的な安心にもつながります。
ただし、土地の所有権を手放すという重要な決断を伴うため、メリットとデメリットをしっかり理解した上で判断することが大切です。そこで、この記事では市道認定の具体的な基準から申請の手順、必要な費用まで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。
私道の維持管理と固定資産税の悩み-市道認定という解決策

自宅敷地や、田舎のご両親の家の私道管理、固定資産税の負担に悩まされることはよくあります。
アスファルトのひび割れや側溝の清掃など、ご自身で対応するには手間も費用もかかりますし、将来のことを考えると「何とかしたい」と悩むこともあるでしょう。
そんな悩みを解決する有効な方法が、私道を市に寄付して「市道」として認定してもらうことです。
この手続きの最大のポイントは、今後の維持管理と税金の負担から完全に解放されることです。
ここでは、市道認定がなぜあなたの悩みの解決策になるのか、その理由を詳しく解説します。
相続した私道の維持管理でかかる負担
私道の維持管理とは、道路の舗装補修や側溝の清掃、除雪(対象地域の場合)などを所有者が自己責任で行うことを指します。
道路のアスファルトがひび割れたり、陥没したりした場合の補修費用は、すべて所有者の自己負担となります。
また、道路の下に埋設されている上下水道管の耐用年数は約40年と言われており、交換には35万円から50万円もの高額な費用がかかるケースもあります。
このような負担が将来にわたって続く可能性があることは、私道を所有し続ける上で大きな悩みとなります。
固定資産税が非課税になる可能性
私道であっても、原則として固定資産税の課税対象です。
不特定多数の人が通行する「公衆用道路」として利用されている場合、自治体に申請することで固定資産税が非課税になることもありますが、必ずしも認められるわけではありません。
その点、市道認定を受ければ、その土地は公共の道路となり、所有権が市に移転します。
この結果、あなたは固定資産税の納税義務者ではなくなり、確実に税金の負担から解放されます。
毎年の固定資産税の支払いがなくなることは、経済的に大きなメリットです。
売買や相続で起こりうるトラブルの防止
私道は、不動産を売買する際に「売却漏れ」という思わぬトラブルを引き起こす原因になることがあります。
「売却漏れ」とは、宅地だけを売買して、それに接する私道の所有権を移転し忘れてしまうトラブルのことです。
実際に新潟市では、20年前に売却したはずの実家の前面道路の所有権が元の売主に残ってしまい、数年後に双方の相続人間で大きなトラブルになった事例が報告されています。
市道認定を受けてあらかじめ所有権を市に移しておくことで、このような将来起こりうる複雑なトラブルを未然に防ぐことができます。
市道認定とセットの寄付採納(無償譲渡)
市道認定を検討する上で最も重要な点が、土地の寄付です。
「寄付採納(きふさいのう)」とは、土地の所有権を無償で市町村に譲渡することを指します。
市道認定は、単に「この道を市道にしてください」とお願いするだけの手続きではありません。
大阪市や新潟市の基準にもある通り、ほとんどの自治体で、道路部分の土地を市へ無償で寄付することが認定の絶対的な条件となっています。
つまり、維持管理や税金の負担から解放される代わりに、あなたはその土地の所有権を手放すことになる、という点を理解しておく必要があります。
市道認定のメリットと知っておくべきデメリット

私道を市道に認定してもらうことで、これまで悩みの種だった維持管理の負担から解放されるという大きなメリットがあります。
一方で、大切な土地の所有権を手放すという決断も伴いますので、メリットとデメリットの両方を正しく理解し、ご自身の状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 維持管理 | 道路の補修や除雪などを市が行う | 個人の意向で整備できない |
| 費用負担 | 補修費用や固定資産税が不要になる | — |
| 権利関係 | 将来の売却漏れや相続トラブルを回避 | 土地の所有権を失う |
| 利用 | — | 通行の拒否ができないなど私権が制限される |
市道認定は、金銭的・精神的な負担を軽くする有効な手段ですが、一度手続きをすると元に戻すことはできません。
長期的な視点で、ご家族ともよく相談した上で検討を進めることをおすすめします。
メリット1-道路補修や除雪などの維持管理からの解放
私道の維持管理は、所有者にとって大きな負担です。
市道に認定される最大のメリットは、この維持管理の責任と費用負担から完全に解放されることです。
これまでご自身で対応する必要があったアスファルトのひび割れ補修や側溝の清掃、さらには除雪対象地域であれば冬場の除雪作業も、すべて市が行うようになります。
福井市の事例でも、道路が傷んだ際の補修は市の責任で行われると示されています。
また、公衆用道路として扱われるため、これまで毎年かかっていた固定資産税が非課税になるという金銭的なメリットも大きいです。
メリット2-上下水道管工事の費用を市が負担
道路の維持管理というと路面の補修ばかりに目が行きがちですが、実は道路の下に埋設されている上下水道管の管理も重要です。
水道管の一般的な耐用年数は約40年といわれており、交換時期が来ると大きな費用が発生します。
私道の場合、この交換費用は所有者の負担となり、ケースによっては35万円から50万円もの高額な出費になることもあります。
市道に認定されれば、この上下水道管の管理や交換工事もすべて市の費用と責任で行われるため、将来発生するであろう突然の高額な出費に対する不安がなくなります。
メリット3-将来の売却漏れや相続トラブルの回避
私道は、将来の不動産売買や相続の際に思わぬトラブルの原因となることがあります。
特に多いのが、建物と宅地だけを売却してしまい、前面道路である私道の所有権を売り忘れてしまう「売却漏れ」のケースです。
新潟市の実際の相談事例でも、売主と買主が代替わりした数年後に、売却されていなかった私道の所有権が発覚し、トラブルに発展しています。
事前に市道認定を受けて所有権を市へ移転(無償譲渡)しておけば、このような複雑なトラブルを未然に防ぐことができ、安心して次の世代へ資産を引き継ぐことができます。
デメリット1-土地の所有権の喪失
市道認定のメリットは大きいですが、その大前提として、道路部分の土地を市へ無償で寄付(寄付採納)する必要があります。
つまり、最も大きなデメリットは、ご自身の土地の所有権を失うことです。
所有権が市へ移転するため、その土地を売却したり、担保に設定して融資を受けたりすることはできなくなります。
あくまでも公共の道路という位置づけになるため、個人の資産ではなくなるのです。
一度寄付採納の手続きが完了すると、原則として元に戻すことはできません。
デメリット2-通行の拒否ができないなどの私権制限
土地の所有権を失うことに伴い、さまざまな私権制限が発生します。
市道認定された道路は、道路法上の「公道」として扱われるため、不特定多数の人が自由に通行できるようになります。
たとえ元々の所有者であっても、特定の人の通行を拒否したり、道路上に車や植木鉢などを置いたりすることはできなくなります。
これまでは私道としてある程度自由に使えていたとしても、認定後は完全に公共の空間として利用方法が制限されることを理解しておく必要があります。
あなたの私道は対象?市道認定の具体的な基準
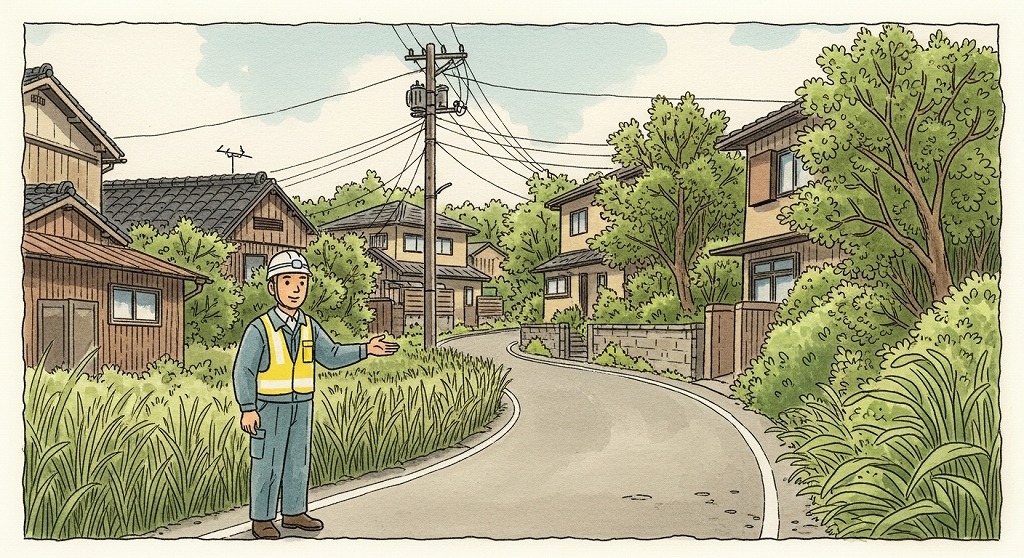
私道を市道として認定してもらうためには、自治体が定める一定の基準を満たす必要があります。実家を相続した方の中には「この私道は市道になるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、市道認定の具体的な基準について、実際の自治体の事例を交えながらわかりやすく解説します。
自治体による基準の違いと事前確認の重要性
市道認定の基準は、道路法に基づきつつも、各自治体が独自に定めている点に注意が必要です。同じ「市道」でも、東京都と地方都市では求められる条件が異なる場合があります。そのため、私道の市道認定を検討する際は、まず管轄の市区町村の道路管理課や建設課に相談し、その地域の基準を確認することが第一歩となります。
事前相談では、対象となる私道が市道認定の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どれくらいの期間がかかるかなどを確認できます。自治体によっては事前調査を実施してくれるケースもあるため、早めに相談することをおすすめします。
基準1-道路の幅員(原則4m以上)
市道認定の最も基本的な条件の一つが、道路の幅員です。多くの自治体では「原則として4メートル以上」という基準を設けています。この幅員は、建築基準法で定められている接道義務の基準とも連動しており、緊急車両の通行や災害時の避難経路としての機能を確保するために必要とされています。
ただし、幅員は道路全体で一定である必要があります。つまり、一部だけ狭くなっている箇所がある場合は、その部分が4メートル未満であれば基準を満たさない可能性があります。また、測定は法敷(のりじき)などを除いた実際の通行可能な部分で行われるため、正確な実測が必要です。
基準2-通り抜けできる道路であること
市道として認定されるためには、道路が公共的な利用価値を持つことが求められます。その重要な要素が「通り抜けできる道路であること」です。具体的には、道路の両端が既存の認定道路(市道、県道、国道など)に接続している必要があります。
ただし、片方の端が認定道路に接続し、もう片方が公共施設に接続している場合や、回転広場が確保されている循環道路の場合など、一定の条件を満たせば認定される場合もあります。袋小路(行き止まり)の道路は、原則として市道認定の対象外となりますが、自動車の回転スペースが確保されているなど、特別な事情がある場合は自治体に相談してみる価値があります。
基準3-所有者や関係権利者全員の同意
私道を市道にするためには、その道路用地の所有者全員の同意が必要不可欠です。これは、私道を市に無償で寄付(所有権を移転)することが前提となっているためです。共有名義の土地の場合は、共有者全員の実印による同意が必要となります。
さらに、道路用地に地上権や借地権などの権利が設定されている場合、それらの権利者からも同意を得る必要があります。抵当権が設定されている場合は、抹消手続きが必要になることもあります。また、相続によって所有権が移転している場合は、まず相続登記を完了させてから市道認定の申請を行うことになります。
隣接地の所有者の同意も重要です。なぜなら、次の基準である「境界確定」の際に、隣接地所有者との立ち会いが必要になるからです。
基準4-境界の確定や排水設備などの構造要件
市道認定を受けるためには、道路と隣接する私有地との境界が明確に確定していることが必要です。境界確定とは、道路管理者(市)と隣接する土地所有者との間で、所有権の境界線について協議し、書面で合意することを指します。この手続きには測量が必要で、通常は土地家屋調査士などの専門家に依頼します。
また、道路の構造も一定の基準を満たす必要があります。主な構造要件には以下のようなものがあります:
- 舗装状態:適切な舗装がされているか、または舗装が可能な状態であること
- 排水設備:雨水などを適切に排水できる側溝やU字溝などの設備が整っていること
- 道路の形状:極端に屈曲していないこと。屈曲がある場合は、適切な隅切り(角を切った形状)が確保されていること
- 支障物件の有無:道路の地下や上空に、電線や水道管などの占用許可が得られない物件が存在しないこと
これらの構造要件を満たしていない場合、市道認定の条件として改善を求められることがあります。改善に必要な費用は、原則として申請者(道路所有者)の負担となります。
大阪市や新潟市の認定基準事例
実際の自治体の基準を見てみましょう。
大阪市の場合、市道認定基準として以下の条件を明示しています:
- 敷地の幅員は原則として4.00メートル以上で一定であること
- 認定する道路の両端が既存の認定道路に接続するもの、または一端が認定道路で他方が公共施設もしくは特に必要と認められる地域に接続するものであること
- 道路の敷地については、原則として所有権を無償で市に移転(寄付)すること
- 道路の敷地については、所有権以外の一切の権利(地上権等の物権及び借地権等の債権)のないものであること
新潟市の場合、市道認定申請は自治会長または町内会長名で行い、以下の書類が必要とされています:
- 市道路線認定同意書(所有者全員の実印が必要)
- 位置図、公図、登記事項証明書
- 寄付申込書や土地所有権移転登記承諾書などの寄付関係書類
また、新潟市では年2回(2月定例会、9月定例会)の市議会で市道認定が審議されるため、申請から認定まで数ヶ月の期間が必要となります。
このように、自治体によって手続きや必要書類、審議のタイミングが異なりますので、早めに管轄の自治体に問い合わせることをおすすめします。
5つの手順で解説-市道認定の申請方法と自己負担費用
私道を市道にするための申請には複雑な手続きが必要です。「何から始めればいいのか分からない」「どのくらいの費用がかかるのか不安」という方も多いでしょう。ここでは、市道認定の申請方法を5つの手順に分けて、初めての方にもわかりやすく解説します。
手順1-役所の担当窓口への事前相談
市道認定の申請を始める前に、まずは管轄の市区町村役所の道路管理課や建設課に事前相談をすることが重要です。この段階で、対象となる私道が市道認定の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、申請から認定までどれくらいの期間がかかるかなど、具体的な情報を得ることができます。
事前相談では、以下の項目について確認しましょう:
- 道路の幅員が基準(原則4メートル以上)を満たしているか
- 道路の両端が既存の認定道路に接続しているか(通り抜けできるか)
- 境界が確定しているか、未確定の場合はどのような手続きが必要か
- 申請に必要な書類の一覧
- 申請から認定までのスケジュール(多くの自治体では年2回程度の議会で審議)
- 支障物件(屋根の越境や私物の設置など)がある場合の改善方法
自治体によっては、事前調査を実施してくれる場合もあります。新潟市の場合、市道認定申請書を提出すると、市の職員が現地調査を行い、道路管理上の支障となるものがあれば改善の条件を提示してくれます。
また、この段階で申請のタイミングも重要です。例えば新潟市では年2回(5月末日締切で9月議会、10月末日締切で翌年2月議会)の申請締切があるため、計画的に進める必要があります。
手順2-境界確定測量と分筆登記
市道認定を受けるためには、道路と隣接する私有地との境界が明確に確定していることが必要です。境界が未確定の場合、この段階で境界確定測量を実施する必要があります。
境界確定測量の流れ:
- 土地家屋調査士への依頼:境界確定測量は専門的な知識と技術が必要なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です
- 資料調査:法務局や市区町村役場で、公図、登記事項証明書、地積測量図、道路台帳図などの関係資料を収集します
- 現地測量:専門の測量機器を使用して、対象地とその周辺を測量します
- 境界立会い:土地家屋調査士、依頼者、隣接地所有者、そして道路との境界確定の場合は市の担当者が現地に立ち会い、境界の位置を確認します。この立会いで全員の合意が得られることが重要です
- 境界標の設置:確認された境界点に永久標(コンクリート杭など)を設置します
- 境界確認書の作成:隣接地所有者全員から署名・捺印をもらい、境界確認書を取り交わします
また、道路用地部分と宅地部分が一筆の土地になっている場合は、分筆登記が必要になります。分筆登記とは、一つの土地を複数の土地に分割する手続きです。市道として寄付する部分と、自分が引き続き所有する部分を分ける必要があるためです。
ただし、新潟市のように「分筆が必要な場合は市が分筆登記を行う」としている自治体もあります。この場合、分筆にかかる費用は市の負担となるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
手順3-関係権利者からの同意書の取得
私道を市道にするためには、道路用地の所有者全員と関係権利者全員からの同意を得る必要があります。これは市道認定の最も重要な要件の一つです。
必要な同意書の種類:
- 市道路線認定同意書:所有者全員が実印を押印して作成します。共有名義の場合は共有者全員の実印が必要です
- 印鑑証明書:同意書に押印した実印の印鑑証明書を添付します(発行から3ヶ月以内のものが一般的)
- 土地登記簿謄本(登記事項証明書):申請する道路用地の全筆について取得します
- 隣接地所有者の同意:境界確定の際に、隣接地所有者からも境界確認書への署名・捺印が必要です
注意したいポイント:
未相続の土地の場合:道路用地の所有者が亡くなっており相続登記がされていない場合は、まず相続登記を完了させる必要があります。相続人全員の同意が必要となり、相続登記の費用は申請者の負担となります。
抵当権などの権利がある場合:道路用地に抵当権や地上権などの権利が設定されている場合、それらを抹消する必要があります。抹消手続きについては、事前に自治体の担当窓口に相談しましょう。
この段階では、隣接地所有者や共有者との円滑なコミュニケーションが重要です。土地家屋調査士に依頼している場合は、専門家として説明や調整をサポートしてくれますが、所有者自身も同行して挨拶することで、スムーズに同意を得られることが多いです。
手順4-必要書類を揃えて市へ申請
境界確定と関係者からの同意が整ったら、必要書類を揃えて正式に市へ申請します。多くの自治体では、自治会長または町内会長の名義で申請することが一般的です。
市道認定申請に必要な主な書類:
- 市道認定申請書(自治体指定の様式)
- 市道路線認定同意書(所有者全員の実印押印)
- 位置図(住宅地図など、申請路線を明示したもの)
- 法務局備付けの公図
- 申請路線の道路用地全筆の登記事項証明書
- 境界確定図(境界が確定している場合)
- 測量図(地積測量図など)
寄付関係の書類(認定の要件に該当した場合):
市の現地調査で認定可能と判断されたら、道路用地を市に寄付するための書類を提出します:
- 寄付申込書(土地所有者ごとに1部、実印押印)
- 土地所有権移転登記承諾書(実印押印)
- 登記原因証明情報(実印押印)
- 印鑑証明書(各所有者分)
- 資格証明書(法人の場合)
- 取締役会議事録等の謄本(法人の場合)
これらの書類は自治体によって多少異なる場合があるため、必ず事前相談で確認した書類リストに従って準備しましょう。
手順5-市の審査と議決を経て正式認定
申請書類を提出した後は、市による審査と議会での議決を経て、正式に市道として認定されます。
認定までの流れ:
- 現地調査:市の担当者が申請場所の状況を確認します。道路管理上の支障物件(屋根の越境、電柱の位置、排水設備の不備など)がある場合は、改善を求められます
- 支障物件の改善:指摘された支障物件がある場合は、期限までに改善工事を行い、市の担当者に確認してもらいます。改善費用は原則として申請者の負担です
- 寄付関係書類の提出:支障物件の改善が完了し、認定の要件を満たしていると判断されたら、前述の寄付関係書類を提出します
- 議会への提案:通常、年2回(2月定例会、9月定例会など)の市議会に市道認定が提案されます。申請から議会での審議まで数ヶ月かかることが一般的です
- 議決と認定告示:議会で議決されると、正式に市道として認定されます。認定告示日(例:新潟市では9月議会提案分は10月1日、2月議会提案分は4月2日)から市道として効力が発生します
- 所有権移転登記:市道認定後、道路用地の所有権を市に移転する登記手続きが行われます
認定が完了すると、申請者(自治会長・町内会長など)宛に市道認定通知が送付されます。これで一連の手続きは完了となります。
自己負担となる費用の内訳-測量費と登記費用
市道認定の申請にあたって、所有者が負担しなければならない費用があります。主な費用は「境界確定測量費」と「登記費用」です。
境界確定測量の費用:
境界確定測量の費用は、土地の状況によって大きく異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです:
- 民間の隣地のみの境界確定:約30万円〜50万円
- 道路(官民)との境界確定も含む場合:約60万円〜80万円
費用に幅がある理由は、以下の要因によって変動するためです:
- 土地の面積(100㎡程度の一般的な住宅用地が基準)
- 隣接地の数(隣接地が多いほど立会いや確認作業が増える)
- 道路管理者との立会いの有無(市道、県道、国道など)
- 境界標の設置数
- 測量の難易度(複雑な形状、高低差がある土地など)
- 隣接地所有者との関係性(トラブルがある場合は時間と費用が増加)
登記関連の費用:
- 分筆登記の費用:境界確定測量とは別に、分筆登記が必要な場合は約10万円〜30万円程度が追加でかかります。ただし、自治体によっては市が負担する場合もあります
- 登録免許税:分筆登記を行う場合、分筆後の土地の筆数×1,000円の登録免許税が必要です
- 相続登記の費用(必要な場合):未相続の土地の場合、相続登記が必要になり、司法書士に依頼すると約10万円〜15万円程度かかります
その他の費用:
- 印鑑証明書や登記事項証明書の取得費用:数千円程度
- 支障物件の改善工事費用:改善が必要な場合(金額は改善内容による)
費用負担を軽減するポイント:
- 複数の土地家屋調査士から見積もりを取る:費用は事務所によって異なるため、複数の見積もりを比較することで適正価格を把握できます
- 境界確定を早めに行う:急いで行う必要が生じると、追加費用がかかる場合があります
- 隣接地所有者との良好な関係を維持する:境界確定がスムーズに進めば、時間と費用の節約になります
なお、道路用地を市に寄付した後の固定資産税は非課税となりますので、長期的に見れば経済的なメリットもあります。
手続きを依頼できる専門家-土地家屋調査士
市道認定の申請プロセスで最も専門性が求められるのが、境界確定測量と登記手続きです。これらの業務を行えるのが「土地家屋調査士」という国家資格者です。
土地家屋調査士とは:
土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにする業務の専門家として、土地家屋調査士法で規定されている国家資格者です。不動産の物理的な状況(位置、形状、面積など)を正確に調査・測量し、登記記録に反映させることが主な業務です。
まとめ

私道の維持管理や固定資産税の負担から解放され、将来の相続トラブルも防げる市道認定は、経済的にも精神的にも大きな安心をもたらす有効な解決策です。
遠方に住みながら私道を管理する負担は想像以上に大きく、アスファルトの補修や側溝の清掃に加え、約40年で訪れる上下水道管の交換時には35万円から50万円もの出費が待ち構えています。
市道認定を受ければ、維持管理責任と費用負担がすべて市へ移り、固定資産税も非課税となります。道路の補修や除雪、上下水道管の交換工事まで市が費用と責任を持って対応するため、予期せぬ高額な出費に悩まされることもありません。所有権を市に移転することで、新潟市で実際に起きたような「20年前の売却時に私道の所有権移転を忘れ、数年後に相続人間で深刻なトラブルに発展した」といった事態も未然に防げます。
ただし、市道認定には境界確定測量(30万円から80万円)などの初期費用がかかり、道路の幅員や通り抜けの可否など満たすべき基準もあります。また、一度所有権を手放すと元に戻せないため、メリットとデメリットを十分に理解した上での慎重な判断が必要です。
あなたの私道が市道認定の対象となるか、手続きにどのくらいの費用がかかるのか、まずは専門家に相談してみませんか。当サイトの無料相談フォームでは、土地家屋調査士や不動産の専門家が、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを提供いたします。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

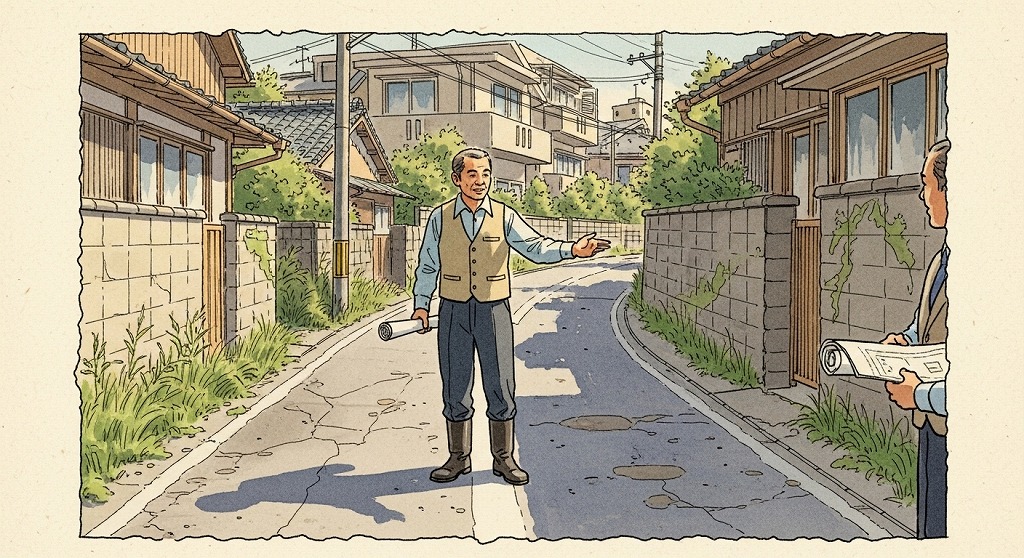


コメント