不動産売買の重要事項説明時などに、たまに出てくる「4項道路」という言葉。聞き慣れない上に、何か特別な事情がありそうで気になりますね。
4項道路とは何かを理解するうえで最も重要なのは、当該土地が「6m区域」という特別なエリアに指定されているというポイントです。
この記事では、4項道路の定義や指定条件といった基本的な知識から、建て替えに大きく影響する2項道路とのセットバック基準の違い、そして役所での具体的な調査方法まで、専門用語を一つひとつ丁寧に解説します。
- 4項道路の定義と指定される条件
- 2項道路とのセットバック基準の違い
- 建て替えできない再建築不可物件になるのか
- ご自身の土地の道路種別を調べる具体的な方法
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。
4項道路とは6m区域で適用される特例的な道路
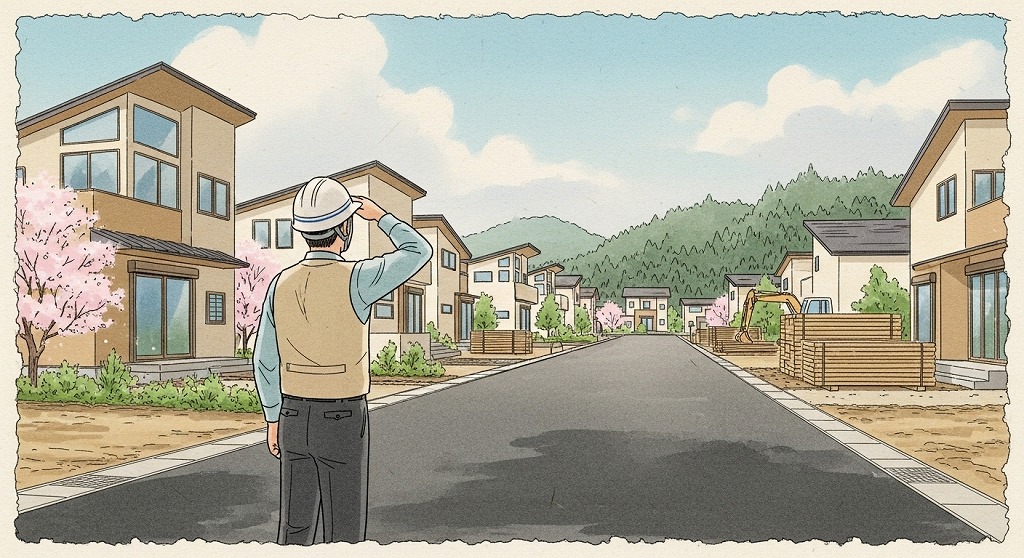
建て替えをご検討されている中で「4項道路」という聞き慣れない言葉が出てくると、ご不安になりますよね。
4項道路とは、特定のエリア内でのみ適用される、少し特殊なルールの道路のことです。
最も重要なポイントは、ご自身の土地が「6m区域」という特別なエリアに指定されているかどうかという点になります。
この「6m区域」が何かを理解することが、4項道路を把握するための第一歩です。
これから、その定義や建て替えとの関係性、そしてなぜこのような特例が存在するのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
建築基準法第42条4項の定義
4項道路とは、法律の言葉でいうと「特定行政庁が指定した『6m区域』内にある、幅員4m以上6m未満の道路」を指します。
これを建築基準法第42条第4項で定めているため、通称「4項道路」と呼ばれているのです。
通常、家を建てる際には幅員4m以上の道路が必要ですが、6m区域では原則として6m以上の幅員が求められます。
しかし、現実的に6mの確保が難しい場合に、避難や通行の安全上支障がないと認められることなどを条件に、特例として建築基準法上の道路とみなされるのがこの4項道路です。
この規定により、建て替え時のセットバック(敷地後退)の基準が変わる可能性があるため、正確な理解が求められます。
建て替えの前提となる接道義務
そもそも、なぜ道路の幅員がこれほど重要なのでしょうか。
それは、建築基準法で定められた「接道義務」があるからです。
接道義務とは、「建物を建てる敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という fundamentalなルールのことをいいます。
この義務は、災害時の消防活動や救急活動、安全な避難経路を確保するために設けられています。
もし、この接道義務を満たさない土地の場合、原則として建物の建築や建て替えができない「再建築不可物件」となってしまうのです。
4項道路は、この厳しい接道義務を6m区域という特殊な条件下で満たすための、例外的な道路の一つとして位置づけられています。
特例が生まれる背景「6m区域」
では、なぜ一部の地域にだけ「6m区域」という、特別なルールが設けられるのでしょうか。
このルールは、その地域の特性に応じて、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)が指定するものです。
法律で定められた用語ではなく、通称として「建築基準法上の道路として認められるために、原則として幅員6m以上が必要とされるエリア」を「6m区域」と呼んでいます。
6m区域に指定される主な理由として、2つのケースが挙げられます。
一つは、埼玉県春日部市のように、細かい開発を防ぎ整然とした街並みを形成するためです。
もう一つは、積雪が多い地域で、冬場の除雪スペースを確保するためといった、地域の気候や土地の状況に応じた理由があります。
このように、4項道路は、良好な市街地環境の形成という目的と、既存の土地利用の現実との間でバランスを取るための、特例的な措置なのです。
全国でも指定事例が非常に少ない実態
ここまで4項道路について解説してきましたが、実は4項道路の指定事例は全国的に見ても非常に少ないのが実情です。
というのも、前提となる「6m区域」の指定自体が、一部の自治体に限られているためです。
例えば、埼玉県春日部市では、2013年10月1日から一部地域で幅員6mの区域が指定されていますが、これは全国的に見ればまれなケースといえます。
建築家の方が「4項道路の可能性がある」と指摘されたとすれば、あらゆる可能性を考慮してのことでしょう。
4項道路が指定される具体的な条件
4項道路はどこにでも存在するわけではなく、いくつかの条件が重なった場合に限り、特例として指定されます。
最も重要なのは、その土地を管轄する「特定行政庁」が指定するという点です。
| 条件 | 概要 |
|---|---|
| 指定主体 | 特定行政庁(建築主事を置く市区町村または都道府県) |
| 道路の幅 | 4m以上6m未満 |
| 安全性 | 通行や避難の安全上、支障がないと認められる |
これらの条件がすべて満たされて初めて、建築基準法第42条第4項の道路として認められます。
そのため、指定されている事例は全国的に見ても非常に少ないのが実情です。
特定行政庁による指定とは?
まず、4項道路の指定を行うのは「特定行政庁」です。
特定行政庁とは、建築確認などを行う建築主事が置かれている市区町村、または都道府県を指します。
国が全国一律で定めるのではなく、その地域の事情をよく知る自治体の判断に委ねられているのです。
例えば、人口25万人以上の市は原則として特定行政庁となり、自らの判断で道路の指定を行います。
したがって、ご自身の土地に接する道路が4項道路に該当するかどうかは、その土地が所在する市区町村役場や都道府県庁に確認する必要があります。
幅員は4m以上6m未満
次に、道路の幅に関する条件があります。
4項道路として指定されるのは、6m区域内にある、幅員が4m以上で、かつ6mに満たない道路です。
これは、建築基準法で定められている道路の原則(幅員4m以上)は満たしているものの、6m区域で求められる基準(幅員6m以上)には達していない、という状況に対応するための規定です。
例えば、幅員が5mの道路であっても、そこが6m区域に指定されていれば、建て替えの際にはこの4項道路の規定が関係してくる可能性があります。
この幅員の条件が、4項道路の特例的な性格をよく表しています。
通行や避難の安全に支障がない
最後に、幅員という物理的な条件だけでなく、実際の機能面も重視されます。
特定行政庁が、周辺の状況から判断して、避難や通行の安全性に問題がないと認めることが必要です。
これは、単に数字上の幅を満たしているだけでは不十分で、例えば、見通しの良さや、緊急車両が通行できるか、袋小路になっていないかなど、地域の安全を守る観点から総合的に判断されます。
万が一の災害時にも住民が安全に避難できる道路でなければ、建築基準法上の道路として認められることはありません。
セットバック基準で比較する2項道路・5項道路との違い
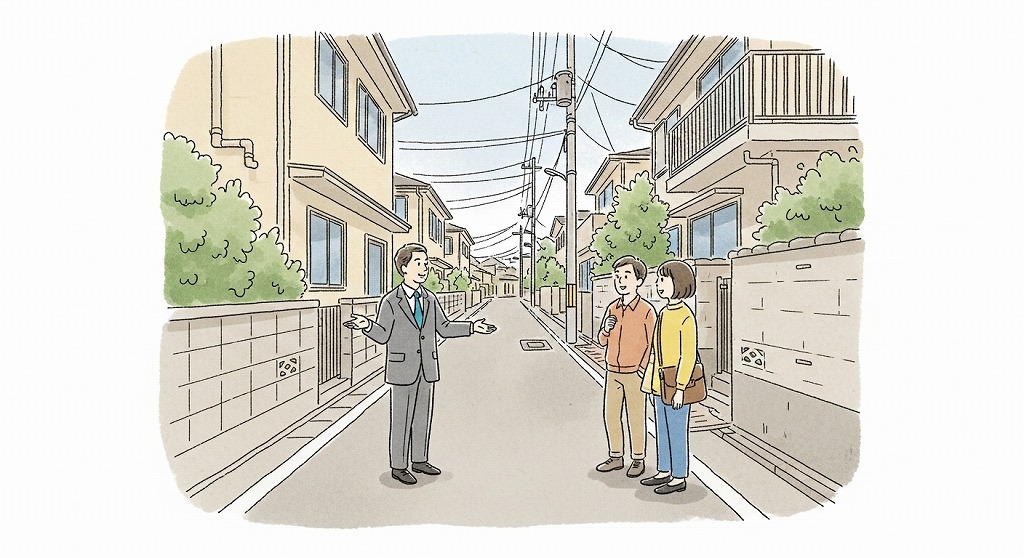
セットバックが必要な道路といっても、いくつかの種類があり、4項道路はそのうちの1つという位置づけです。
特に4項道路は特殊なため、他の道路との違いを押さえておきましょう。具体的な建築計画を立てるうえで、正しい知識は必ず役立ちます。
| 道路の種別 | 対象となるエリア | 道路の幅員 | セットバックの基準(中心線から) |
|---|---|---|---|
| 2項道路 | 全国 | 4m未満 | 2m |
| 4項道路 | 6m区域内 | 4m以上6m未満 | 3m |
| 5項道路 | 6m区域内 | 4m未満 | 3m |
この表からわかるように、ご自身の土地が「6m区域」に指定されているかどうかで、後退しなければならない距離が変わってきます。
道路の中心線から2m後退する2項道路
2項道路とは、建築基準法第42条第2項で定められた道路のことです。
古くからある住宅地などでよく見られ、通称「みなし道路」と呼ばれています。
この道路は、建築基準法が施行された1950年11月23日より前から建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを指します。
建て替えを行う際には、道路の中心線から水平距離で2m後退した線を道路の境界線とみなす「セットバック」が必要です。
セットバックによって後退した敷地は、道路の一部として扱われます。
そのため、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積には含まれず、門や塀などを建てることもできなくなります。
同じ6m区域内で幅員4m未満の5項道路
5項道路は、建築基準法第42条第5項で定められた道路を指します。
4項道路と同じく「6m区域」内でのみ適用される点が特徴で、6m区域が指定された際にすでに存在していた幅員4m未満の道路が該当します。
4項道路と同様に、建て替え時には道路の中心線から水平距離で3mの位置まで敷地を後退させる必要があります。
これにより、将来的に道路の幅員を6m確保することを目指しています。
4項道路との決定的な違いは、道路の「幅員」です。
幅員が4m以上6m未満であれば4項道路、4m未満であれば5項道路に分類されると覚えておきましょう。
建築基準法上の主な道路の種類一覧
ここまで見てきた道路以外にも、建築基準法ではさまざまな種類の道路が定められています。
ご自身の土地に接する道路がどれに該当するかを把握することは、円滑な不動産取引や建築計画の基礎となります。
| 道路の種別 | 内容 |
|---|---|
| 42条1項1号道路 | 国道、県道、市道などの道路法による道路(幅員4m以上) |
| 42条1項2号道路 | 都市計画法や土地区画整理法などによって造られた道路 |
| 42条1項3号道路 | 建築基準法施行時に既に存在した幅員4m以上の道路 |
| 42条1項4号道路 | 2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
| 42条1項5号道路 | 民間が申請し、行政から位置の指定を受けて造られた私道(位置指定道路) |
| 42条2項道路 | 幅員4m未満で特定行政庁が指定した、いわゆる「みなし道路」 |
| 42条4項道路 | 6m区域内で特定行政庁が指定した幅員4m以上6m未満の道路 |
| 42条5項道路 | 6m区域指定時に存在した幅員4m未満の道路 |
これらの複雑な道路種別は、ご自身で判断するのは困難です。
次の章で解説する調査方法に沿って、役所の担当窓口で正確な情報を確認することが重要になります。
土地に接する道路の種別を確認する調査方法
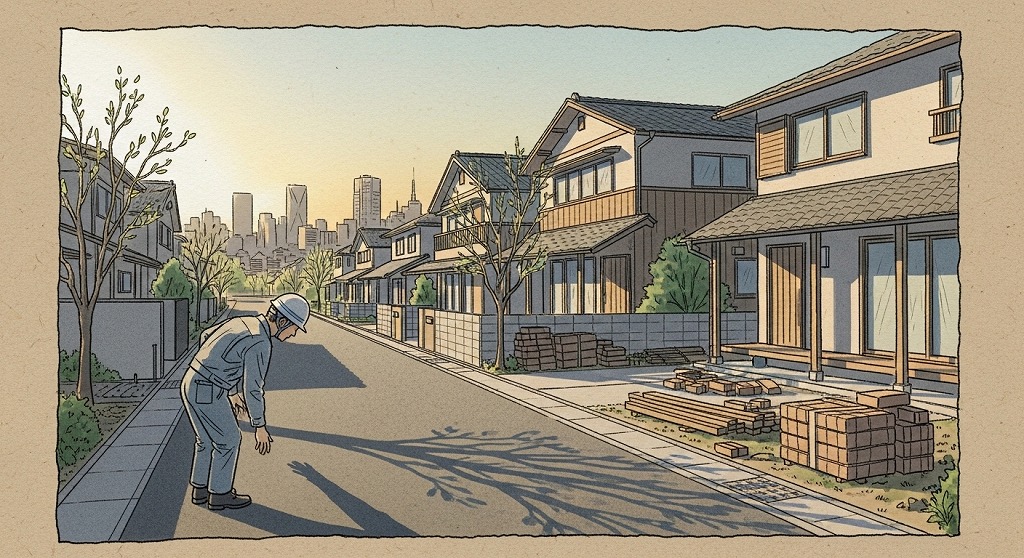
ご自身の土地に接する道路がどの種類に該当するのか、不安に思うお気持ちはよくわかります。
しかし、ご安心ください。
道路の種別は、ご自身で調べることが可能です。
専門家任せにせず、役所で公的な資料を確認することが、正確な情報を得るための最も確実な方法となります。
ここでは、誰でもできる調査の手順を3つのステップで解説します。
この手順に沿って確認すれば、ご自宅の建て替え計画を安心して進められるようになります。
役所の担当窓口で相談
まず初めに行うことは、お住まいの市区町村役場の担当窓口へ行くことです。
建築基準法上の道路に関する情報は、「建築指導課」「道路管理課」といった部署が管轄しています。
どの部署か分からない場合は、総合案内窓口で「建築基準法上の道路種別について確認したい」と伝えれば、適切な部署へ案内してくれます。
相談に行く際は、ご自宅の住所や地番がわかる登記簿謄本や公図の写しを持参すると、手続きがスムーズに進みます。
専門の職員に直接質問できるため、疑問点をその場で解消できるのが大きな利点です。
道路台帳や道路調査図を閲覧
担当窓口では、「道路台帳」や「道路調査図」といった資料を閲覧できます。
これらは、道路の状況を記録した公的な図面で、道路の幅員や種類が明記されています。
ご自宅の場所を伝えれば、該当する図面を見せてもらうことが可能です。
資料の中には、「建築基準法第42条第1項1号」や「同条第2項」のように道路の種別がはっきりと記載されています。
ご自身の土地が4項道路に該当するのか、それとも他の道路なのかをこの資料で確定させます。
閲覧は基本的に無料で、自治体によってはコピーを取得することもできます。
現地で道路の幅員を実測
役所で道路台帳を確認した後は、念のため現地で実際の道路幅を測っておきましょう。
なぜなら、台帳に記載された計画上の幅員と、実際の幅員が異なっているケースがあるからです。
建築確認申請の際には、現況が重視されるため、事前の確認が重要となります。
測る際は、ご自宅の敷地に接している道路の端から反対側の端までをメジャーで実測します。
1カ所だけでなく、数カ所の幅員を測っておくと、より正確な状況を把握できます。
この一手間が、後々の設計変更などのトラブルを防ぐことにつながるのです。
よくある質問(FAQ)

- Q「4項道路」と聞きましたが、私の土地は建て替えできない「再建築不可」物件になるのでしょうか?
- A
いいえ、ご安心ください。
4項道路は建築基準法で正式に認められた道路です。
そのため、この道路に2m以上接している敷地であれば、接道義務を満たしており、原則として「再建築不可」にはなりません。
ただし、建て替えの際には、道路の中心線から3m後退するセットバックが必要になる場合があります。
これにより、利用できる敷地面積が少し狭くなる可能性がありますが、建物を新しく建築することは可能です。
- Q4項道路に面した土地は、将来売却する際に価値が下がりますか?
- A
4項道路に面していること自体が、不動産の価値を大きく下げる直接的な原因になることは少ないです。
なぜなら、建築確認を取得して合法的に建物を建てられる土地だからです。
しかし、セットバックによって有効に使える敷地面積が減少する点は、評価に影響します。
売却する際は、道路の種別やセットバックの有無といった条件を不動産会社を通じて購入希望者に正確に伝えることが、円滑な取引の鍵となります。
- Q自分の土地が「6m区域」に指定されているか、簡単な確認方法はありますか?
- A
最も確実な確認方法は、土地がある市区町村の役所(建築指導課など)で確認することです。
役所には道路台帳が備え付けられており、ご自身の土地が6m区域に含まれるか、また接している道路の詳しい種別を正確に知ることができます。
自治体のウェブサイトで都市計画図を公開している場合、そこで大まかなエリアを確認できることもあります。
しかし、最終的な判断は必ず役所の窓口で、最新の公式情報に基づいて行ってください。
- Q2項道路と4項道路のセットバックの違いを、もっとわかりやすく教えてください。
- A
一番の違いは、後退しなければならない距離です。
2項道路は将来的に幅員4mの道路にすることを目指しているため、道路の中心線から「2m」後退します。
一方で、4項道路は「6m区域」という特別なエリアにあるため、将来的に幅員6mの道路にすることを目指しています。
そのため、道路の中心線から「3m」後退するという、より厳しい条件が定められているのです。
目指す道路の幅が違う、と覚えるとわかりやすいです。
- Q4項道路と、よく聞く「位置指定道路」は同じものですか?
- A
いいえ、これらは全く別のものです。
4項道路は、もともと存在する道を、その地域の特性に合わせて特定行政庁が「建築基準法42条4項の道路」として指定します。
それに対して位置指定道路は、主に私道で、土地の所有者が宅地開発などのために新たに道路を造り、特定行政庁から「建築基準法42条1項5号の道路」として位置の指定を受けたものを指します。
指定される経緯や根拠となる法律の条文が異なります。
- Q建築確認の申請手続きにおいて、4項道路で特に注意すべき点は何ですか?
- A
建築確認を申請する際には、まず接道している道路が4項道路であることを役所の資料で証明する必要があります。
その上で、設計図面はセットバック後の敷地を前提として作成しなければいけません。
後退した部分は建築面積や建ぺい率・容積率の計算に含めることができず、門や塀なども設置できないため注意が必要です。
設計を依頼する建築士に、道路調査の結果を正確に伝え、法的な条件を遵守した計画を進めることが重要になります。
まとめ

この記事では、建て替え計画で重要な4項道路について、その定義から2項道路との違い、ご自身でできる調査方法まで解説しました。
4項道路を理解するうえで最も大切なのは、ご自身の土地が「6m区域」という特別なエリアに指定されているかという点です。
- 特定行政庁が指定する「6m区域」内にある幅員4m以上6m未満の道路
- 建て替え時に必要な道路中心線から3mのセットバック
- 接道義務を満たしているため再建築は可能
- 役所の担当窓口での道路台帳による正確な調査
建て替え計画を安心して進めるために、まずはこの記事で解説した手順に沿って、役所でご自身の土地に接する道路の種別を確認することから始めましょう。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。





コメント